| イベント・見学会 2010年度 | |
| 2022年度 ←… 2019年度(10周年) ←…… ←←次年度 | |
|
|
|
| 研究室のイベントを紹介します。見学会では地下鉄福大前駅の見学をしました。 |
|
|
|
|
| ■行事 | |
| ■第1回研究室懇親会(2010.5.27)を「よしず」で行いました。辰巳先生はじめ、仲間の意外な面が分かり楽しい会でした。 |
|
 |
|
|
|
|
| ■第2回研究室懇親会(2010.8.11)を「朝次郎 大名店」で催しました。学生より研究室の仲間と一緒に何かしたいという意見が出され、地下鉄「福大前」駅構内およびトンネル内の見学会が、9月3日に実現しました。 ■第3回研究室懇親会(2010.12.22)を「鉄なべ餃子」で催しました。卒業論文作成の追い込みの時期でしたが、それは忘れての楽しい忘年会でした。 |
|
 |
|
|
|
|
| ■第4回研究室懇親会(2011.2.10)を「博多虎鉄」で催しました。この会は卒業論文発表会の打ち上げで、達成感・満足感とともに学生生活への別れを感じる会でした。 |
|
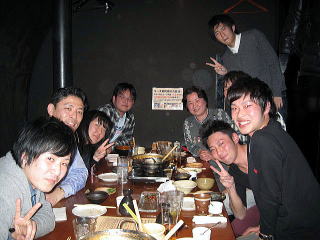 |
|
|
|
|
| ■土木学会西部支部研究発表会(2011.3.5)で香口さんと岡君が発表しました。みんなで九州工業大学戸畑キャンパスへ行きました。発表は上手でしたが、優秀賞は取れませんでした。残念。 |
|
  昼食後で発表前です。前列中央が岡君と香口さんです。学会終了後です。お疲れ様でした。 |
|
|
|
|
| ■卒業式(2011.3.19)の謝恩会での記念写真です。有意義な楽しい一年でした。社会人になる人、大学院で勉強を続ける人、明日から新たな第一歩です。 |
|
 |
|
|
|
|
| ■見学会 | |
| 地下鉄七隈線「福大前」駅でトンネル内保守作業などの見学をしました。 | |
| ●日時 ●見学場所 ●案内者 ●見学内容 |
2010年9月3日(金) 24:00 ~ 9月4日(土 )2:00 地下鉄七隈線「福大前」駅 福岡市交通局 稲田さん・山口さん ①地下鉄七隈線の概要 ②福大前駅のバリアフリー設備 ③駅員の夜間業務内容 ④地下の換気 ⑤トンネル内の保守作業 |
| ①地下鉄七隈線の概要 最初に地下鉄七隈線が造られる背景の説明を受けました。費用便益効果は1.6倍であり、事業費用を早く回収するために、福岡市地下鉄は東京や大阪の地下鉄に比べて運賃が高いそうです。(でもバスよりは安い・・・) 七隈線ではシールド工法とNATM工法、開削工法が採用されています。土地の特性によって使い分けられており、シールド工法とNATM工法の丁度境が福大前にありました。トンネルの上部に円形と四角ではっきりと境目が分かりました。(暗くて写真が撮れずに残念) また七隈線は空港線・箱崎線と異なり、リニアモーターシステムが採用されており、トンネルの大きさも空港線・箱崎線に比べて直径で1m以上小さいそうですが、大きく感じました。 ②福大前駅のバリアフリー設備 音声案内や展示案内といったバリアフリー施設が充実していました。なかでも最も印象に残ったものは音声案内掲示板でした。音声機能掲示板には駅構内のマップが示されていて、マップ内のトイレや改札口、切符売り場のボタンを押すと目的地まで音声案内してくれる機能を有していました。この音声案内機能付案内板は天神南駅と福大前駅にのみ設置されているそうです。 ③駅員の夜間業務内容 駅員の方から夜間業務について伺いました。夜間の業務は2人で行い、勤務時間は朝の9時までです。最終電車が発車した後は、居残りのお客さんがいないか念入りに見回りをして、その後、駅に宿泊します。宿泊理由は火災報知器の誤作動や地震、大雨などの非常事態に対処するためで、そのために駅にはシャワーも備えています。(宿泊施設は見せてもらえませんでした。) 駅員には委託社員の方もおられ、制服が違うそうです。運転手はJRのOBが多いそうです。 最後に、福大生は酒に酔って最終電車を遅らせたり、駅内にゲロを吐いたりする人が多いという耳の痛いお話も伺いました。(駅を清潔に保ちたい、掃除が大変というお話に、ただただ申し訳ない気持ちで一杯でした。) ④地下の換気 |
|
概要説明 |
|
| 駅の機械室 |
|
| 点検作業車と終電後の線路上 |
|
| 点検作業車の出発とリニアモーターシステムのリアクションプレート |
|
| 見学終了 |
|
| 昼間の外の猛暑に比べて、地下は快適と思い込んでいました。そのために夜間のトンネル内は涼しいくらいの気持ちで臨んだ見学会でした。 ところが、営業の終わった地下鉄駅構内およびトンネル内の暑さには参りました。汗がポタポタでマイッタマイッタ。 夜間作業員の方々の仕事の大変さに加えて、暑さとの戦いの仕事に頭が下がります。多くの人に支えられている地下鉄です。大いに利用します。 |
|
|
|
|
←←次年度← |
|